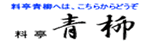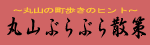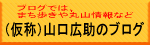|
平成14年8月10日よりカウンター開始しました。
|
|
|
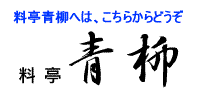
この「広助の『丸山歴史散歩』」は、長崎の名所旧跡史跡を毎日更新
でお届けしております。 コースはA〜Eまでの5コースで、A:長崎駅〜県庁〜日見峠、B:蛍茶屋〜田上、C:唐八景〜丸山〜戸町、D:思案橋〜出島〜浦上、E:稲佐〜神の島です。
|
|
|
(仮称)山口広助のブログ |
 平成25年 〜2013年〜
平成25年 〜2013年〜